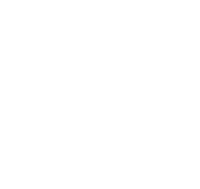第27回映画祭TAMA CINEMA FORUM
プログラム紹介
【B-3】人生を見つめ直して
人生フルーツ

- 2016年/東海テレビ放送製作/東海テレビ放送配給/91分
- 監督=伏原健之
- プロデューサー=阿武野勝彦
- 撮影=村田敦崇
- 音楽=村井秀清
- 音楽プロデューサー=岡田こずえ
- 編集=奥田繁
- ナレーション=樹木希林
- 出演=津端修一、津端英子
ストーリー
コツコツ、ゆっくり……樹木希林さんのナレーションで始まる。雑木林に囲まれた一軒の平屋に住むのは、建築家の津端修一・英子夫妻。四季折々、庭を彩る70種の野菜と40種の果実。長年連れ添った夫婦の歴史――台湾との繋がり、人間らしく暮らせる設計の仕事。そして現在の暮らしを丹念に描き出す。
コメント
もう何度かご覧になった方も多いのではないだろうか。樹木希林さんの穏やかなナレーションも相まって、一度観ただけでも私たちは津端家の親戚にでもなったかのような気になってしまう。暖かく迎え入れてくれる家屋。次々と出てくる心のこもった料理。機織り、畑仕事。その暮らしには、夫・修一さんが住宅設計で培ってきたことや叶わなかったこと、台湾からの少年兵とどう関わってきたか、またはその惨い再会、楽しみのヨットのこと、そしてそこにはいつも英子さんがいたことが詰まっている。修一さんの最後の仕事は、患者たちが人間らしい暮らしができるような精神病院の設計だった。謝金や設計料をいっさい辞退し、引き受けたのだった。しかし、それは亡くなる2か月前。完成は英子さんが見届けることとなる。日本ではどれほどの人々が箱物の施設に入っているのだろう。施設を捨てよ町に出よう、仕事をしよう、暮らそう。津端夫妻のように。終盤、庭の水盤が割れるシーンがある。その時の英子さんの言葉と表情が、今までの気丈さが一瞬壊れ、修一さんを失ったこと、何か時が経てありようが移ろっていくことへの悲しみを表しているように思われ、忘れられない。(小)
この世界の片隅に

- 2016年/「この世界の片隅に」製作委員会製作/東京テアトル配給/126分
- 監督・脚本=片渕須直
- 原作=こうの史代
- 企画=丸山正雄
- プロデューサー=真木太郎
- キャラクターデザイン・作画監督=松原秀典
- 美術監督=林孝輔
- 音楽=コトリンゴ
- 声の出演=のん、細谷佳正、尾身美詞、稲葉菜月、牛山茂、新谷真弓、岩井七世
ストーリー
昭和19年広島、すず18歳。降って湧いたような縁談にいざなわれるまま呉へと嫁ぎ、夫・周作とその家族とのひとつ屋根の下での生活が始まった。戦局は悪化の一途をたどり徐々に閉塞感が漂うなか、それでもささやかな幸せを噛み締めながら日常を過ごしていく。しかし、無情にも時代の流れは牙を剥いて襲い掛かってきた。
コメント
以前に比べればきな臭くなってきた昨今とはいえ、兵士でもない自分たちの頭上にある日突然無数の飛行機が現れて、爆弾を落としていく光景をリアルに想像できる人はそういないのではないだろうか。おそらく当時の人たちもそうだったはずだ。これはあまり知られていないように思われるが、実は一般人が本格的な空襲にさらされたのは終戦前のほんの1年弱の間のことであった。劇中でも描写されているようにそれまでは、水準こそ異なれど、家事・勤務・食卓の団欒など今の我々と変わらない生活サイクルがそこにあった。多くがモノクロであるせいか戦前戦中の画像・映像を見ても現在と切り離してとらえがちだが、総天然色でビビッドに甦った光景をあなたが普段見ている空や大地と重ねてみてはいかがだろうか。
ところで、本作は一般の方々から出資を募って(いわゆるクラウドファンディングによって)制作された。原作の読者でもありながら出資し損ねてしまったのが返す返すも悔やまれる。(中)