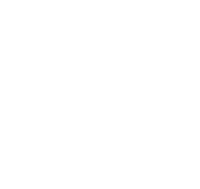第27回映画祭TAMA CINEMA FORUM
プログラム紹介
【C-3】短編映画祭「コテクール」セレクション‐日仏映画交流‐(共催:広島国際映画祭)
短編映画祭「コテクール(Côte Court)」とは
1992年からパリ郊外のパンタンの映画館「Ciné 104」にて毎年6月に行われている映画祭。フランス製作作品のみをコンペティションで扱い、また通常中編として扱われる60分程度の作品も「短編」として位置づけて、幅広いセレクションを行っている。フランソワ・オゾン(『婚約者の友人』)、ラリユー兄弟(『愛の犯罪者』)、セバスチャン・ベベデール(『メニルモンタン 2つの秋と3つの冬』)、アルチュール・アラリ(『汚れたダイヤモンド』)…etcといった監督たちを多数輩出している。
住民総会

- Assemblee generale
- 2014年/フランス/17分
- 監督=リュック・ムレ
- 出演=パスカル・ボデ、ヴァレリー・ブスケ、サビーヌ・パコラ
ストーリー
小部屋で行われる23戸の住民総会は、電気料金の設定や古いトイレの解体など、問題山積である。
コメント
今年80歳を迎えたヌーヴェル・ヴァーグの作家リュック・ムレによる本作は、老齢にしていやそれだからこその軽やかな笑いが止まらない傑作短編である。まとめ役の男の電話が鳴る。カエルの鳴き声の着信音だ。フロッグは英語でフランス人の蔑称でもあり、先ずフランス人を笑っている。赤ちゃんが泣いても誰もあやさない。編み物をする女、イヤホンで電話する男、近視で眼鏡のない男。それぞれがなんだか笑える。電気料金を払わない頑固な人。中国人を黄色いゴミ箱と掛けている人がいてレイシストだと叱られている。17分のなかで次々と展開する人々のやり取りが人間臭く可笑しいのである。一つ一つ、一言一言すべてに意味があるようだが、それらがわからなくても楽しめる。住民総会が終わらずに部屋から出られない人たち。最後に乱入するのは……。(小)
思い出の風景画

- Le Tableau
- 2013年/フランス/30分
- 監督・脚本=ローラン・アシャール
- 製作=ラジ・ベルケイ
- 撮影=ジョルジュ・ディアン、レミ・メストレ
- 編集=ネリー・オリヴォール、カトリーヌ・クズマン
- 音響:エマニュエル・ヴィラール、アニエス・ザボ
- 出演=テレーズ・ルーセル、フレッド・ペルソンヌ、パスカル・セルヴォ
ストーリー
老夫婦マルセル(F・ペルソンヌ)とオディール(T・ルーセル)は静かな時間を過ごしていたが、妻オディールの入院を翌日に控えていた。入院を前にオディールに会おうと人々が訪ねてくるが……。
コメント
マルセルのオディールへの何気ない仕草と気遣いに二人の親密さが垣間見える。もちろん彼は彼女の病状を知っているだろう。大事にしていたワインを開けたように、彼は何かを覚悟しているようだ。絵画を譲る約束をしたオディールにも覚悟が見て取れる。
小さな鶏舎の雄鶏が度々登場する。それが老夫婦の前に姿を見せるとき、それを目の当たりにするのはオディールだけである。本来ならば夜明けを告げ希望の象徴とも言える雄鶏が、死へと誘う使者に見える。
物悲しく不穏な雰囲気に覆われた物語は、何が起きたかも定かではない奇妙な展開を見せる。その結末は決して不幸には見えない。それは、たとえ人生の終わりが近づいても、彼らには鮮烈で色褪せない二人の物語の始まりの記憶があるから。
絵画は時が経つにつれ当時の色合いは失われていく。それでも心のなかの絵画は永遠に瑞々しく美しいままだ。(遠)
物語を求めて

- Vous voulez une histoire?
- 2014年/フランス/10分
- 監督・脚本・撮影・音響・編集=アントナン・ペレジャトコ
- 出演=ポーリーヌ・ゲルシ、ルシ・ボルトー
ストーリー
物語を求めて、2人の女を乗せた汽車が世界へ出発する。
コメント
型破りなフレンチ・コメディの傑作長編を生み出したペレジャトコ監督による短編作品は、何とも不思議な映像紀行である。冒頭のテロップで物語の定型的な語り口「昔々」が否定され、即座に旅が始まる。断片的なプライベートビデオのような世界各地の映像が軽妙なナレーションと共に次々に映し出される。いつ日本に来たのかわからないが、突然日本の都会と被災地の映像が出て来るのには驚いた。何となくクリス・マルケル風の作品と形容することもできるだろうが、本作は映像それ自体には重きを置かず思索的でもない。むしろ映像を用いて語る遊びの愉楽がこの作品の魅力だろう。「物語」という紋切り型の形式に安住することなく、観客を異邦人の眼差しと共に、更なる物語への冒険へと誘う。(佐)
ユーグ

- Hugues
- 2017年/フランス/48分
- 監督・脚本=パスカル・セルヴォ
- 撮影=ラファエル・ヴァンデンブッシュ
- 編集=マルシャル・サロモン
- 音響=ロザリー・リヴォイル
- 出演=アルノー・シモン、ガエタン・ヴルチ、ドミニク・レイモン
ストーリー
引退した40歳の舞台俳優ユーグ(シモン)は、彼の生家でパートナーのセルジュ(ヴルチ)と共に暮らしていた。しかしそこにやってきた演出家のミシュラン(レイモン)が、彼に再び俳優を続けるべきだと主張し、一冊の脚本を手渡す。ユーグが家でリハーサルをしていると、庭に隣接した牧草地で楽しむ裸の人々を発見する。
コメント
ポール・ヴェッキアリやローラン・アシャールといった巨匠監督作品の常連俳優パスカル・セルヴォが監督した長編第3作は、何ともたわやかで知的なユーモア溢れる作品である。冒頭の暗い部屋の中から窓、カーテン、そして奥の遠景を捉えた端正なショットは、そのまま映画全体の優美さを貫く。その調和を打ち破るような突然のヌーディストの登場には、思わず吹き出してしまった。家の中でパートナーと静かな生活を送ろうとしていたユーグと外で開放的に楽しむヌーディストたちとの間の境界が、抵抗空しく徐々に崩されていくさまは、何とも滑稽である。クスッとした笑いもあれば、一転ホラーのような不気味さを漂わせたり、人生の悲哀を感じさせたりと、シーンによって異なる複雑なエモーションを演出する手腕は見事。2017年グランプリ受賞作品。(佐)
ゲスト紹介

ジャッキー・エヴラール 氏
「コテクール」の創設者でありアーティスティック・ディレクター。1980年代にクレテイユそしてブリュノワ映画祭のプログラマーを経て、パンタンの映画館「Cine104」の館長となる。エピネー=シュール=セーヌ短編映画祭が92年に終了したと同時に、パンタンの地でそのバトンを引き継ぐ。以降今日まで25年以上に渡って、創造性の高い短編映画を生み出す映画監督たちを奨励し続けている。

パスカル・セルヴォ 監督
カトリーヌ・コルシニ監督『Les Amoureus(恋人たち)』(1994年)にて映画俳優デビュー。その後、ローラン・アシャールやポール・ヴェッキアリ、ピエール・レオン、ヴァレリー・ムレジャンらの監督作品に出演。初監督した2008年の短編『Valerie n’est plus ici』はコテクールで受賞し、13年に第2作『Monsieur Lapin』を監督している。『ユーグ』は彼の監督第3作である。