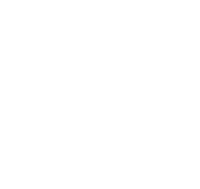第27回映画祭TAMA CINEMA FORUM
プログラム紹介
【C-13】三宅唱監督のまなざし
やくたたず

- 2010年/PIGDOM配給/76分
- 監督・脚本・撮影・編集=三宅唱
- 音楽=片方庸介
- 出演=柴田貴哉、玉井英棋、山段智昭、片方一予、櫛野剛一、足立智充、南利雄
ストーリー
12月の札幌を舞台に、高校卒業を間近に控えたテツオら3人は、地元の先輩・伊丹が勤める防犯警備会社に通い始める。同僚・京子や刑事の次郎らの不安をよそに、仕事の役に立とうと車の運転を教えてもらい、無為に過ごす時間を抜け出そうとするが……。一面雪に覆われた北海道を舞台に、若者たちの切実な一瞬を美しいモノクロームの映像できりとった青春映画。波のように跡形もなく消えていく時間が鮮烈な印象を残す。村上淳、加瀬亮などの俳優に絶賛された、三宅唱監督の恐るべき初長編作品。この映画から傑作『Playback』が生まれた。
コメント
20代半ばの三宅唱監督が監督、脚本、撮影、編集を一人で行い、わずか5人のスタッフで2010年に手がけた初長編作品。この時、もうすでに自然のなかで移ろう人間の動きや、その人自身の魅力を余すことなくとらえる様子が画面に焼き付けられている。
冒頭、ざらりとした白黒の世界を風が吹きすさぶなか、三者三様に歩く若者の姿にはしてやられたとしか言いようがない。真っ白な雪を踏みしめながら、学ランの男たちが野良犬のような面構えで野兎のようにあたりを飛び跳ねるさま。バイト先の警備会社の先輩をみて変わろうと願いつつも、変わってたまるかという苛立ちも感じた。卒業間際、残された時間に限りがあることを考えないようにしながらも、いつものようにツレとたわむれ、やることなすこと味わってやろうという瑞々しさ。男たちは燃費が悪くても、ガス欠しても、でこぼこ道であってもハンドルを握って車を走らせていく。
劇中では、現場に向けて発進した車に置いてけぼりにされた男が、雪に足をとられながら斜面を駆け上がり車の後ろから頭を突っ込むながれをみて、雪原のサッカー中継を思い出した。また、荒れ狂う海沿いを、言葉を交わすでもなく延々と歩く男2人を観て、とうとうここまで来てしまったのかという思いが頭をもたげてしまった。労働であっても気の合う仲間がいることで生まれる波打つような躍動感もあれば、寄せては返すモノクロの陰影にさらわれる不安が渦巻くこともある。
戻りようのない高校時代に、これから生きていく世界へ向ける冷静な視線。何者にもなれない焦りと、つまらん奴にはなりたくないかすかな意地。気づけば散り散りになり、残っているものすべてが無駄に愛おしい。(内)
リンク
NAGAHAMA / 八月八日

- NAGAHAMA
- 2016年/Pigdom製作・配給/18分
- 監督=三宅唱
- 撮影=四宮秀俊
- 協力=SUPER TRAMP
- 挿入歌=優河「青の国」
- 出演=石橋静河
- 八月八日
- 2016年/Pigdom製作・配給/13分
- 監督= 三宅唱
- 撮影= 四宮秀俊
- 協力=SUPER TRAMP
- 出演= 石橋静河
ストーリー
幼少時よりバレエ、ダンスを続けてきた女優の石橋静河と、三宅唱監督と撮影の四宮秀俊によるコラボレーションから生まれた2本の短編作品。日常にあるさまざまなからだの動きとダンスの運動との行き来によって、映画における魅力的なからだのあり方を一緒に探ってゆく。
コメント
『映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ』ではせわしない東京の雑踏に覆われ、不安と喪失が隣り合うぎりぎりのところに立っている姿をみせ、『PARKS パークス』では亡き父の昔の恋人として、今とつながる過去に井の頭公園で歌に思いをのせる若者の姿を演じていた。
『NAGAHAMA』と『八月八日』は、匿名性をまとった石橋静河の生身の身体の息づかいがそっとひそやかに始まり、そこはかとない気配があたりに漂っていく。浜辺と室内というそれぞれ限定された場所で石橋静河のみが佇み、ゆらめく身体の鼓動と垣間見える芯の強さ。空間における体をその動きとともにみつめるカメラ、それらを劇場の暗闇で観る者たちの目。女優と一個人の境界を越えて、自分の体ひとつで波にたゆたうように祈りを捧げる彼女を通して、観客自身も感覚が研ぎ澄まされていく。来年公開の『きみの鳥はうたえる』では、どのような姿をみせるのか。その予感に満ちた短編というにはもったいない、この深みに没入してほしい。静河という名のとおり、ゆっくりと流れる川面に響く波紋とともに……。(内)
密使と番人

- 2017年/時代劇専門チャンネル、日本映画専門チャンネル製作/アルタミラピクチャーズ、ピグダム制作/60分
- 監督・脚本=三宅唱
- 脚本=松井宏
- 撮影=四宮秀俊
- 音楽=OMSB、Hi'Spec
- 出演= 森岡龍、渋川清彦、石橋静河、井之脇海、足立智充、柴田貴哉、嶋田久作
ストーリー
人里から切り離された冬の山。男たちは自らの使命のため、黙々と歩みを進める──
19世紀はじめ、鎖国下の日本。開国を望む蘭学者の一派が、幕府管理下にある日本地図の写しを密かに完成させる。彼らはオランダ人にその地図の写しを渡すため、若い蘭学者の道庵(森岡)を密使として出発させる。身を潜めながら、山の中を進む道庵だが、高山(渋川)をはじめとするその山の番人たちは、幕府が手配した道庵の人相書を手に山狩りを始めていた……。
コメント
歴史の事実として起きたことや、実際にそこにいた人々が毎日何を感じてどう過ごしていたかを想像することは難しい。ただ、人が悩みながらも日々の営みを続けていたことは確かなことだ。
劇場の闇に身を預けて、山にうごめいている自然や人間たちの息づかいに耳をすませることで、感覚が開かれていく。劇中の幾重にも重なる音、光、人の動きを全身で感じることで、今の自分たちの生活に手触りのある実感をたぐりよせていける。
本作では江戸から遠く離れ、冬の厳しい山に紛れ込んだ密使が道なき道を歩き、番人たちが迫っていく。開国前夜の歴史が揺れ動くなか、大きな理想を傍らに携えて誰にも知られず、ずたぼろになりながら彷徨う男。GPSも携帯電話もなく、人相書という超絶アナログな手がかりのみで徒手空拳で追うしかない番人たちのつらさ。権力やそれに抗う者たちとは関係なく、自然相手に暮らす夫婦の日々の厳しさ。
永遠に続いていくような雪原を踏みしめる人間はちっぽけで、ぶつかりあい苦悶する肉体のおかしみと哀しさ。そこでは物言わぬ自然が眼前に横たわり、止まっているように見えて時間とともに表情を変える山と太陽、行く手を阻むススキは侵入者も追跡者も問わず惑わし、川の水の冷たさはささくれた心にしみいる。今は空気のようにある電気も何もないなか、柔らかな夕日差し込む森が闇夜に包まれ、朝焼けに染まり、動物の挙動がそこにある強さにしびれてしまう。
鎖国を解かれて160年ほどたった現在。あいも変わらず、人はそれぞれの論理であくせく動き回っている。それを風景のように眺める山の動じないさまよ。(内)
リンク
監督紹介

三宅 唱 監督
1984年札幌生まれ。『やくたたず』(2010年)ののち、劇場公開第1作『Playback』(12年)を監督、同作はロカルノ国際映画祭に正式出品され、高崎映画祭新進監督グランプリ、日本映画プロフェッショナル大賞新人監督賞を受賞。『THE COCKPIT』(14年)は国際ドキュメンタリー映画祭シネマ・デュ・レエル新人監督部門に正式出品。ほかに「無言日記」(boidマガジンにて連載中)など。雑誌「POPEYE」にて映画評「IN THE PLACE TO C」を連載中。2018年には最新作『きみの鳥はうたえる』を公開予定。