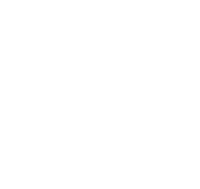第26回映画祭TAMA CINEMA FORUM
プログラム紹介
【B-6】スクリーンで輝く若手男優
葛城事件

- 2016年/「葛城事件」製作委員会製作/ファントム・フィルム配給/2時間
- 監督・脚本=赤堀雅秋
- プロデューサー=藤村恵子
- 撮影=月永雄太
- 美術=林千奈
- 音楽=窪田ミナ
- 編集=堀善介
- 出演=三浦友和、南果歩、新井浩文、若葉竜也、田中麗奈
ストーリー
金物屋を営む葛城清(三浦)は妻・伸子(南)と2人の息子に恵まれ、念願のマイホームを建てたが、気づかぬうちに抑圧的に家族を支配するようになる。ある日、伸子は次男の稔(若葉)を連れて家出する。そして、迎えた家族の修羅場……。
コメント
ひとつのテーブルを家族で囲む食事のシーン、父親の「お家に帰ろう」というセリフが絶望へと導いていく。普通の幸せな家族ドラマでは、同じセリフで心温まるのに、このシーンの重さが葛城家を物語っている。「家族」という狭い環境下での行き詰った重い空気、無差別殺人事件、そして死刑と目を背けたくなるほど悲惨な物語であるのに他人事と思えないのが怖い。日々のふとした生活のほころびが破滅に繋がるのかもしれない。今、普通に生活していることが奇跡のように感じる。
葛城家は特別異常ではなかったと思う。愛もあり幸福な時間もあった。いつまでも現実に向き合おうとせず、お互いに目を背け、少しの歯車のきしみがゆっくりと崩壊へと導いていく。切っても切れない「家族」という繋がりは時に残酷である。
“食べる”ことは大事だと思った。人が作ってくれた温かいものは美味しい。(都)
セトウツミ

- 2016年/映画「セトウツミ」製作委員会製作/ブロードメディア・スタジオ配給/1時間15分
- 監督・脚色=大森立嗣
- 原作=此元和津也
- プロデューサー・構成・脚色=宮崎大
- プロデューサー=近藤貴彦
- 撮影=高木風太
- 音楽=平本正宏
- 編集=早野亮
- 出演=池松壮亮、菅田将暉、中条あやみ、鈴木卓爾、成田瑛基, 岡山天音, 奥村勲、牧口元美、宇野祥平
ストーリー
調子が良く童貞感丸出しの瀬戸(菅田)と、常に達観していて学校のマドンナに好かれている内海(池松)が二人で喋る。とにかく喋る。ひたすら喋る。それをひたすらに観る、それだけのシンプルな作品だ。
コメント
瀬戸が直球なら内海は変化球を投げるように逆の雰囲気を持ちつつも、放課後を持て余しただただ時間を過ごす、たまたま利害が一致しただけとは思えないような絶妙なバランスである。そして時間が経つにつれ、二人が互いを好きなのがとてもよくわかる。それだけでなく観客もこの二人の会話を好きになってしまうのだ。可愛くてしょうがない。私は瀬戸と内海に会いに2回は観に行ったし、なんなら2回目の方が次に何が来るのかわかっているのに面白い……くらい。この放課後は永久に続くようで……いや、それは高二マジックなのだけど、二人の空気と時間に愛おしさを感じずにはいられない。自分もこういう時間を過ごしてきただろうし、いつまでも二人のように他愛もない話をグダグダ話しながら生きていきたい。(菊)
走れ、絶望に追いつかれない速さで

- 2015年/Tokyo New Cinema製作・配給/1時間23分
- 監督・脚本=中川龍太郎
- プロデューサー=藤村駿
- 撮影・編集=今野康裕
- 音楽=酒本信太
- 出演=太賀、小林竜樹、黒川芽以、藤原令子、寉岡萌希、松浦祐也
ストーリー
青春時代を共に過ごした親友・薫(小林)の死を受け入れられないでいる漣(太賀)は、何にも感情が動かない日々を過ごしている。ある日、漣は薫の元恋人・理沙子(黒川)と共に旅に出る。
コメント
どこかの部屋、布団と紙が映し出される場面からこの物語は始まる。薫の“死”に向き合いながら、自身の“生”に向き合っていく話である。
あったかいご飯を食べるということは、お腹を満たすということは、すなわち生きることなのだ。お腹が満たされると心も満たされる気がする。人の優しさに気付けたり、優しくなれたり、美しいものを美しいと感じたり。“食べる”ことは“生きる”ことと直結している。ボロボロのアパート、まるごと頬張ったトマト、銭湯に響く声、自転車で下った坂道、屋上で見た朝日。なんでもないけれど、なんでもないからこそ、愛おしく思える日々。そんな日々を思い出しながら観てほしい。そして、彼らと同世代の方々にはもっと観てほしい。観終わったあと、ああ、映画っていいなあ……としみじみ思う、そんな一本。(志)
ゲストの紹介

中川 龍太郎 監督
1990年神奈川県生まれ。詩人としても活動。著作に「詩集 雪に至る都」(2010年)。第2回詩とファンタジー年間優秀賞受賞(10年)。国内の数々のインディペンデント映画祭にて受賞を果たす。『Calling』(12年)がボストン国際映画祭で最優秀撮影賞受賞。『雨粒の小さな歴史』(12年)がニューヨーク市国際映画祭に入選。東京国際映画祭日本映画スプラッシュ部門では『愛の小さな歴史』(14年)に続き、『走れ、絶望に追いつかれない速さで』(15年)が2年連続の出品を最年少にして果たす。