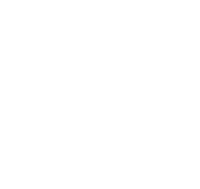第26回映画祭TAMA CINEMA FORUM
プログラム紹介
【C-1】ブリィヴ・ヨーロッパ中編映画祭セレクション -日仏映画交流- -Vol.1-
小規模ながらいまヨーロッパで最も脚光を浴びている映画祭の一つである「ブリィヴ・ヨーロッパ中編映画祭」特集プログラム。過去3年の同映画祭作品のなかから厳選した日本未公開5作品を2日に渡ってお届けします。特集初日の本プログラムでは2011年グランプリ作品『女っ気なし』も上映いたします。
ブリィヴ・ヨーロッパ中編映画祭とは
2004年に始まった同映画祭は、長編でも短編でもない「中編」(30〜60分)を対象にしているのが特徴。世界三大映画祭(カンヌ、ヴェネツィア、ベルリン)や、より先鋭的な作品を選出するロカルノ映画祭でも集まりにくい、ヴァラエティに富んだ新たな才能に出会える映画祭として注目されています。同映画祭出身の若手映画作家の躍進を評した「ブリィヴ世代」という言葉も生まれた。
女っ気なし

- Un monde sans femmes
- 2011年/フランス/エタンチェ配給/58分
- 監督・脚本=ギョーム・ブラック
- 共同脚本=エレーヌ・リュオ
- 撮影・音楽=トム・アラリ
- 編集=ダミアン・マイストラジ
- 出演=ヴァンサン・マケーニュ、ロール・カラミー、コンスタンス・ルソー
ストーリー
純朴で不器用な独身男性シルヴァン(V・マケーニュ)は、ヴァカンスでやってきた若い母娘(L・カラミー、C・ルソー)にアパートを貸す。3人はお酒を飲んだり海水浴をしたりと仲良く過ごしていたが、そこに彼の友人ジルが現れて……。
遭難者

- Le naufrage
- 2009年/フランス/エタンチェ配給/25分
- 監督・脚本=ギョーム・ブラック
- 撮影=クロディーヌ・ナットキン
- 編集=ダミアン・マイストラジ
- 出演=ジュリアン・リュカ、アデライード・ルルー、ヴァンサン・マケーニュ
ストーリー
フランス北部の小さな町で、自転車がパンクしたリュック(リュカ)。通りすがりの地元の青年シルヴァン(V・マケーニュ)が彼を助けようとするが……。『女っ気なし』のプロローグ的短編。
コメント
親切でやさしいのだけど、どこか人との距離感がずれているシルヴァンが愛らしい。現実にいたら少し疎ましく思ってしまうかもしれないが、映画だともっと寄り添ってみたくなるのが映画の素晴らしいところ。彼の繊細な心の揺れがひしひしと伝わって来て、他人事とは思えなくなってしまう。
『遭難者』は、彼の神出鬼没な登場シーンからおかしくて心を掴まれる。人恋しくて世話焼きな彼の急な距離の詰め方が、端的に表現された見事な切り返しショット!彼のおせっかいで、リュックは恋人との関係が動き出す。
タイトルの「遭難者」とは、自転車のパンクしたリュックではなくシルヴァンのことかもしれない。彼は人生の路肩で誰かと繋がれることをひたすら待ち続けている。
『女っ気なし』は、ロジエやロメール作品のようなヴァカンス映画の魅力が溢れている。酒を飲みながら興じるジェスチャー大会の笑いの絶えないおかしさ、そして明るく澄み渡った浜辺で伸びやかで肉感的な肢体を晒す女たちの眩さ。シルヴァンが心の奥の湿った孤独感をその夏の陽射しの元へ開こうとしているところに、友人のジルが現れて4人の関係が激しく動き出す。
ヴァカンスはいつだって夢のようにはかない。その幸福の残り香を抱きしめて引き留めようとも。
娘のジュリエットを演じたコンスタンス・ルソーは、黒沢清監督『ダゲレオタイプの女』(2016年)に主演している注目の若手女優である。(佐)
グッドナイト・シンデレラ

- Boa Noite Cinderela
- 2014年/ポルトガル/30分
- 監督・脚本=カルロス・コンセイサオ
- 撮影=ヴァスコ・ヴィアナ
- 美術=ジョアン・ルイ・ゲーラ・ダ・マタ
- 衣装・メークアップ=リタ・アルバレス・ペレイラ
- 編集=カルロス・コンセイサオ、アントニオ・ゴンサルヴェス
- 出演=ジョアン・カシューダ、ダヴィッド・カベシーニャ、ジョアナ・デ・ヴェローナ
ストーリー
シンデレラ(J・ヴェローナ)は、真夜中にガラスの靴の片方を残して城から逃げ去る。その翌日から王子様(J・カシューダ)は、その両靴を揃えたいという気持ちを抑えられずにいる。
コメント
かの有名な童話「シンデレラ」がモチーフのコスチュームプレイ(衣装劇)。しかしディズニー的な甘いファンタジーのそれではなく、シンデレラが残した靴を拾った王子様がその靴の持ち主を探し求める部分のみをアレンジした、少し風変わりな作品である。
残されたガラスの靴を手に入れた王子様は、蝋燭を灯して森の奥へと進んでゆく。彼を魅了し、彼を突き動かす情熱とは一体……。
凝った衣装と照明が醸し出す、気品とキッチュが混じった魅力は、オリヴェイラやモンテイロ作品を彷彿させる。美術は、ジョアン・ペドロ・ロドリゲス監督(『鳥類学者』(2016年)でロカルノ映画祭監督賞受賞)作品のプロダクションデザインを手がけているジョアン・ルイ・ゲーラ・ダ・マタが担当。ポルトガルの新たな才能に要注目である。(佐)
ルピーノ

- Lupino
- 2014年/イタリア、フランス/49分
- 監督=フランソワ・フェレラッチ、ローラ・ラマンダ
- 撮影=フランソワ・フェレラッチ
- 録音=ウーゴ・カサビアンカ、ヴィンセント・プルポニア、レミ・ゴーティエ
- 編集=ローラ・ラマンダ
ストーリー
アンソニーとオルスそしてピエール・マリーは、「ルピーノ」というコルシカ島の郊外の地域に住んでいる。彼らが育った公営住宅は、海や繁華街や他のあらゆる場所から離れた、鉄道と丘の間に閉じ込められた場所にあった。夏が来ると、彼らは街へ繰り出す。彼らは公共ベンチや不毛な土地で忙しい日々を一緒に過ごす。何かのまぼろしや仲間、そして抜け出すことに憧れながら。
コメント
デスメタルが流れる禍々しいオープニングクレジット。続く少年たちを背後から追った長回しのシークエンスから、凡百のドキュメンタリーとは一線を画す異様な迫力が伝わってくる。
「ルピーノにあるのは幹線道路だけで、普通の道路も路地も広場もない。公共交通機関も存在しないため、若者の多くはしばしば歩き回って、毎日あてどなくさまようことを強いられている。サッカーをするにも、友だちに会うにも、たむろする場所を見つけるにもかかる長い歩行は、ほとんど叙事詩的な旅である。」(監督インタビューより抜粋)
現代の秘境で監督が長い時間を彼らと過ごして捉えた、コルシカ島の「囚人たち」の姿。いままで誰も見てこなかった彼らのヴァイタリティが強烈に伝わってくる。(佐)
ギャング

- GANG
- 2015年/フランス/36分
- 脚本・監督=カミーユ・ポレ
- 撮影=ジュリエット・バラ
- 編集=マリルー・ヴェルジュ
- 出演=ピエール・デスプラ、シャルロット=ヴィクトリア・ルグラン、カミーユ・ポレ、レオ・リチャード、ベンジャミン・アムリ、エイドリアン・ピーター、ジェレミー・ゴーチェ
ストーリー
フランス北部の海辺で、ある友だちのグループにもうすぐ別れが訪れようとしていた。ピエール(C・ルグラン)は、とある病気を患っていて街を去ろうとしている。
コメント
ハイビジョン映像が主流ないま敢えて選択されたビデオ撮影。それは、本作の時代設定を反映している。本作が描く2002年と1984年の2組の若者たちの物語。80年代当時はエイズが不治の病であった時代であり、VHSが一躍勢力を拡大していた時代でもあった。
2002年のもうすぐ18歳を迎える若者たち。そこにいる「ピエール」という男性的な名前を持つ少女は、とある病気を患っていてその治療のために街を去ろうとしている。1984年の物語、女一人と男二人の共同生活。仲の良い彼らに訪れる苦難。恋愛と友情、決別と連帯。そして2002年の物語へと繋がる。
ビデオ特有のざらついた色の沈んだ映像の質感は、鮮烈さと引き換えに、登場人物たちにそっと寄り添うような親密な感触を生み出している。それぞれの時代で訪れる人と人との「別れ」。それは同時に、大人へと成長し新たな出会いを生む、自らの幼い時代との別れでもある。(佐)