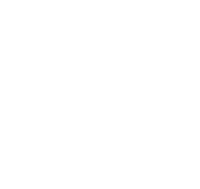第26回映画祭TAMA CINEMA FORUM
プログラム紹介
【B-7】楽しきかな団地生活
海よりもまだ深く

- 2016年/フジテレビジョン、バンダイビジュアル、AOI Pro.、ギャガ製作/ギャガ配給/1時間57分
- 監督・脚本=是枝裕和
- プロデューサー=松崎薫、代情明彦、田口聖
- 撮影=山崎裕
- 照明=尾下栄治
- 美術=三ツ松けいこ
- 音楽=ハナレグミ
- 出演=阿部寛、真木よう子、小林聡美、リリー・フランキー、池松壮亮、吉澤太陽、橋爪功、樹木希林
ストーリー
15年前に文学賞を1度とったきりの良多(阿部)は、探偵事務所での稼ぎをギャンブルにつぎ込み、息子・真吾(吉澤)の養育費も払えず別れた妻・響子(真木)にも愛想を尽かされていた。月に一度の親子の面会の日、母・淑子(樹木)の家に集まった良多と響子と真吾は台風のために帰ることができなくなり、久々に家族で一夜を過ごすことになる。
コメント
人生は思い通りにいくことばかりではない。主人公の良多が文学賞を受賞したのは遠い昔、妻と息子と家族であったことも既に過去だ。けれども人生はこれからも続いていくし、家族でなくなったとしても、父と息子が親子であることは変わらない。
一度も登場しない父のことが、映画のなかでは繰り返し語られる。「親父みたいになりたくなかった」良多はそう言うが、そんな親子にも似ているところがある。台風の夜に起こったできごとは、良多と真吾の似ていないところによって生まれたものだった。しかし、家族でなくなった彼らが台風の夜に過ごした時間は、きっとかけがえのない思い出になるのだろう。
終始ダメ男として描かれる良多だが、嫌いだったはずの父の思いに出会った時、少しだけ成長を見せる。家族でなくなった親子はどう生きるのか。夢見た未来ではないかもしれないが、台風が過ぎ去った朝の街で、こわれてしまった家族の未来が少し明るく見え、思わず泣けてしまう。(尾)
団地

- 2016年/「団地」製作委員会製作/キノフィルムズ配給/1時間43分
- 監督・脚本=阪本順治
- 製作総指揮=木下直哉
- プロデューサー=武部由実子、菅野和佳奈
- 撮影=大塚亮
- 美術=原田満生
- 音楽=安川午朗
- 編集=普嶋信一
- 出演=藤山直美、岸部一徳、大楠道代、石橋蓮司、斎藤工、冨浦智嗣、濵田マリ、原田麻由
ストーリー
三代続いた漢方薬店をたたんだヒナ子(藤山)と夫(岸部)は、団地に越してきた。やがて夫は床下にこもるようになり、団地に住む人々の噂話の餌食になる。漢方薬を求めて夫妻のもとをたびたび訪れる青年(斎藤)にはある秘密があった……。
コメント
なにはともかく、藤山直美、岸部一徳、大楠道代、石橋蓮司をはじめとして、でてくる役者たちが皆芸達者で、その演技のアンサンブルを観ているだけで楽しくなる。市井の人々の描写にリアリティがあるので、後半現実を超越した世界が現れてきても観客はそれを素直に受け入れることができる。藤山直美が最初に脚本を読んだ際、後半の展開に驚いて、監督に「病院に行った方がよいのでは」と進言したとの逸話が残っているが、阪本監督は出演する役者たちのもつ演技の「力」を信じてこのテーマを選んだのだと思う。
この夫婦のように家族や周囲の人々に対して純粋な愛を貫いていても、それを遠巻きに見ている住民からえげつない詮索や吹聴で貶めていかれるが、客観的に且つコミカルに描かれているので、それも世の常と思えてくる。終盤、この夫婦に救いの瞬間が訪れる。日常の生活に追われていると目の前に起こる出来事にしか目がいかなくなるが、天から俯瞰してみればそれはこっけいなことであり、真理は存在するのだということにこの作品は気づかせてくれる。感謝。(淳)