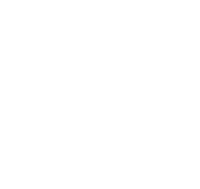第35回映画祭TAMA CINEMA FORUM
プログラム紹介
【D-14】団地団 多摩の団地映画を語る+世界は団地でできている
チケット情報
-
一般
前売 1,200円
当日 1,400円 -
子ども(4歳~小学生)
前売 800円
当日 900円 -
支援会員特別料金1,000円
-
障がい者特別料金
- 付添者1名も同一料金
1,000円
インターネットで購入
窓口で購入
[休館日と祝日を除く。休館日:第1木曜、第3木曜]
※「【A-1】第17回TAMA映画賞授賞式」のチケット購入については販売方法が異なりますので専用ページをご確認ください。
[休館日と祝日を除く。休館日:第1月曜、第3月曜]
※「【A-1】第17回TAMA映画賞授賞式」のチケット販売はございません。
会場アクセス
ベルブホール
小田急多摩線/京王相模原線「永山駅」より徒歩2分。ベルブ永山5階
どこまでもいこう

- 1999年/ユーロスペース、映画美学校製作・配給/75分
- 監督・脚本=塩田明彦
- プロデューサー=堀越謙三、松田広子
- 撮影=鈴木一博
- 美術=磯見俊裕、三ツ松けいこ、露木恵美子
- 音楽=岸野雄一
- 編集=筒井武文
- 出演=鈴木雄作、水野真吾、鈴木優也、芳賀優里亜、津田寛治
ストーリー
郊外のニュータウン。同じ団地に住むアキラと光一はいつものように連れ立って小学校に向かう。今日は5年生の新学期が始まる日。学校ではクラス替えが発表されている。体育教師に予告されたとおり、コンビで悪さをするふたりは別々のクラスになってしまった。それからふたりの関係には微妙なずれが生じ始める。ふたりの関係の変化が子供時代から大人へと脱皮していく少年たちとともに描かれていく。
コメント
多摩市が舞台のこの作品は26年前の永山の団地風景がロケ地として多く使用されている。多摩映画祭35周年で団地団が語るにはピッタリすぎる作品。
大人になりきれない子どもたちの鬱屈(うっくつ)感が団地という迷路のなかを走り続ける。余計なセリフをそぎ落とした乾いた画面がこの作品の完成度の高さを物語っている。全編に流れる「史上最大の作戦」のマーチが頭を混乱させる。等身大の少年、少女たちの毎日が時に無邪気に、時に残酷に進んでいく。内気な少年とのささやかな交わりが重い結末を残していく。これが大人への通過儀礼としたら、未来への扉はとてつもなく重い。少年たちはどこまでもいけたのだろうか。多摩にこんなにもハードな団地映画が残されていたことをあらためて嬉しく思う。上映当日、団地団のトークと共に35mmフィルムの画面でしっかりと確認してほしい。(昇)
団地団
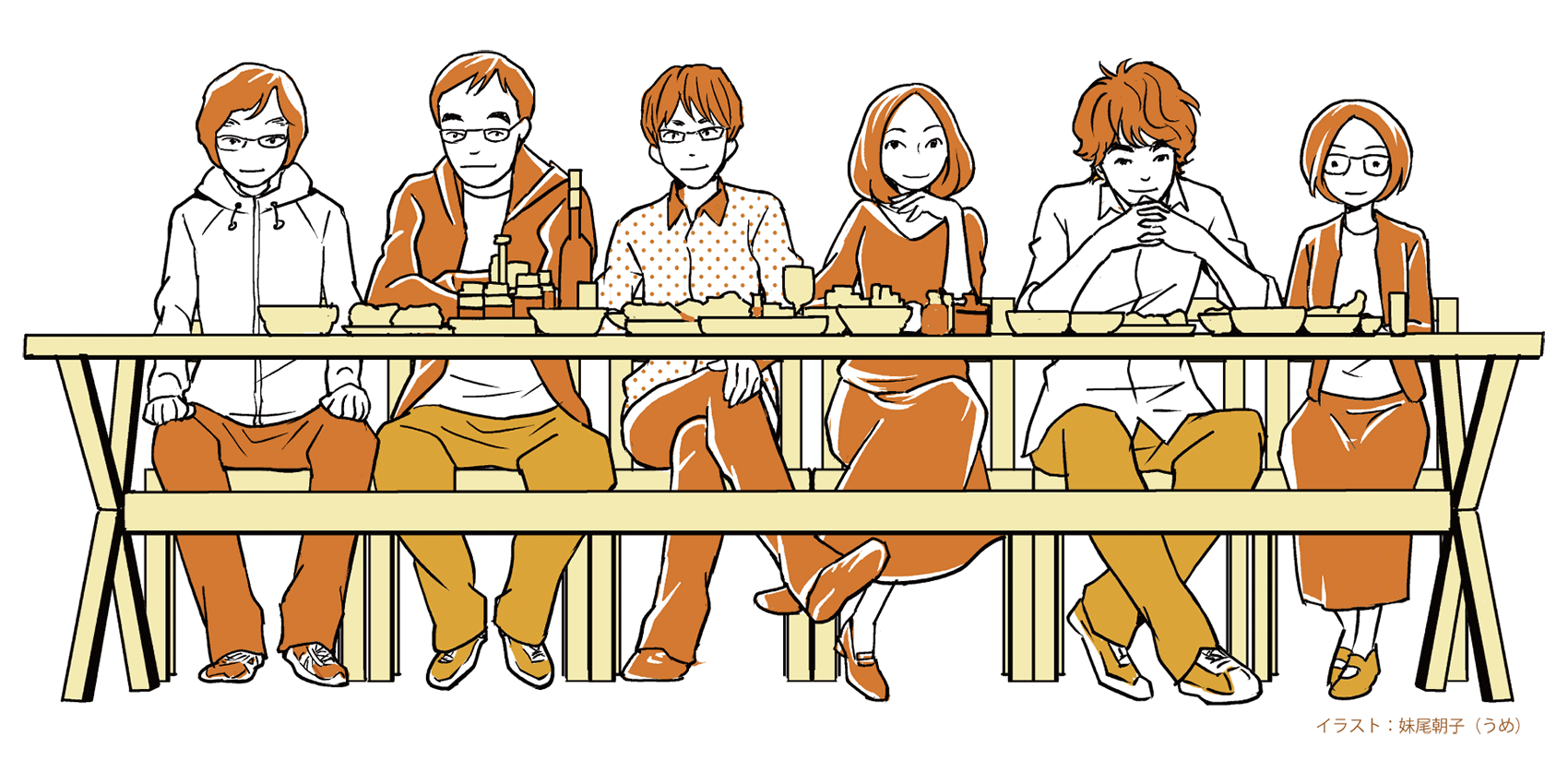
2010年12月、新宿ロフトプラスワンのトークイベントで結成。メンバーがそれぞれの立場から、映画、マンガ、アニメなどに登場する団地について深く考察して大放談を繰り広げる。話題は団地の美観や構造に対する偏愛にとどまらず、団地登場作品の演出論から大衆文化論、果ては都市論や郊外論にまで飛び火。知恵熱必死の知的エンターテインメント集団。
ゲスト紹介

大山 顕 氏
1972年生まれ。写真家/ライター。「住宅都市整理公団」(団地マニアのための団体。2000年に設立。団員は2人)の総裁。10年に佐藤大、速水健朗とともに「団地団」を結成。主な著書に「団地の見究」、「マンションポエム東京論」、「工場萌え」(石井哲との共著)、「新写真論」など。

佐藤 大 氏
1969年生まれ。脚本家。代表作にアニメ「カウボーイビバップ」(98年)、「交響詩篇エウレカセブン」(2005年)、映画『サイダーのように言葉が湧き上がる』(21年)、『映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021』『ぼくらのよあけ』(いずれも22年)、TVアニメ「ポケットモンスター」(23年~)、「T・Pぼん」(24年)、「LAZARUS ラザロ」(25年)などがある。

稲田 豊史 氏
1974年生まれ。ライター・コラムニスト・編集者。映画配給会社、出版社を経て独立。主な著書は「ぼくたちの離婚」「映画を早送りで観る人たち ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形」「ポテトチップスと日本人 人生に寄り添う国民食の誕生」。最新刊は「ぼくたち、親になる」。団地団との出会いは、出版社の社員だった2011年に足を運んだ団地団トークライブの第2回。ライブ終了後、トーク内容の書籍化をメンバーに直接もちかけ、「団地団 〜ベランダから見渡す映画論〜」の企画・編集を担当(12年に刊行)。13年の独立を機に正式メンバーへと昇格した。

速水 健朗 氏
ライター・編集者。ラーメンからショッピングモールまであれこれ執筆。たまにテレビやラジオのコメンテイターなどもやってます。主な著書に「ラーメンと愛国」「バンド臨終図巻」など。愛車は黄色の日産マーチ・カプリオレ。

妹尾 朝子 氏
企画・シナリオ・演出担当の小沢高広、作画・演出担当の妹尾朝子からなる二人組漫画家。代表作「大東京トイボックス」シリーズ。そのほか「ちゃぶだいケンタ」「南国トムソーヤ」「きょくまん」「STEVES」「おもたせしました。」「アイとアイザワ」「ブラガール」など。現在は育児エッセイマンガ「ニブンノイクジ」やWeb漫画サイト「ビッコミ」にて「南緯六〇度線の約束」を連載中。2016年「団地団」へ入団。

山内 マリコ 氏
1980年生まれ。富山県出身。作家。大阪芸術大学映像学科卒。2008年「女による女のためのR-18文学賞」読者賞を受賞し、12年「ここは退屈迎えに来て」でデビュー。16年に刊行した「あのこは貴族」が岨手由貴子監督によって映画化され、21年TAMA映画賞最優秀作品賞を受賞。ぴあフィルム・フェスティバル2025では審査員を務めた。近刊に「マリリン・トールド・ミー」「逃亡するガール」「地方女子たちの選択」(上野千鶴子氏との共著)など。今秋、対談集「きもの、どう着てる? 私の「スタイル」探訪記」が発売。